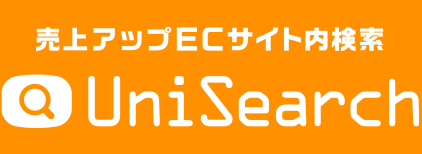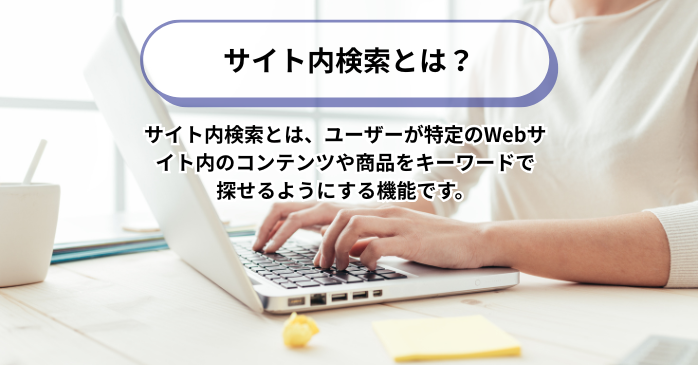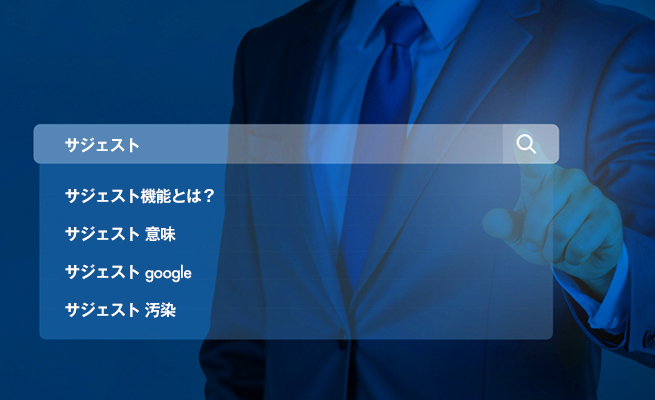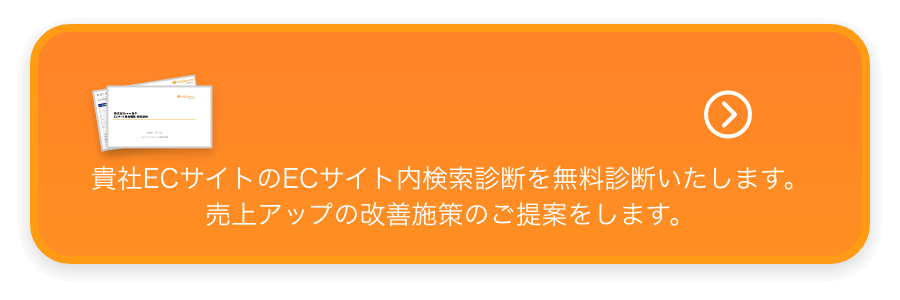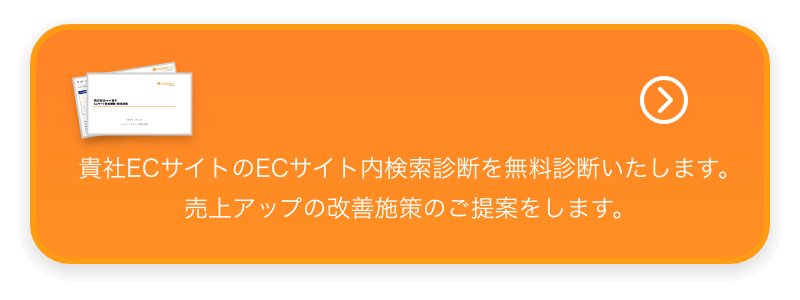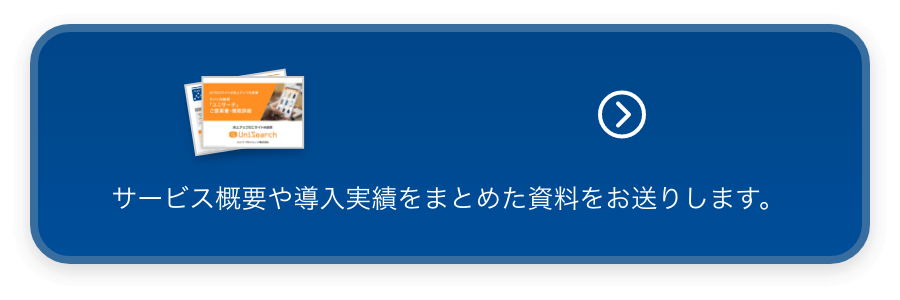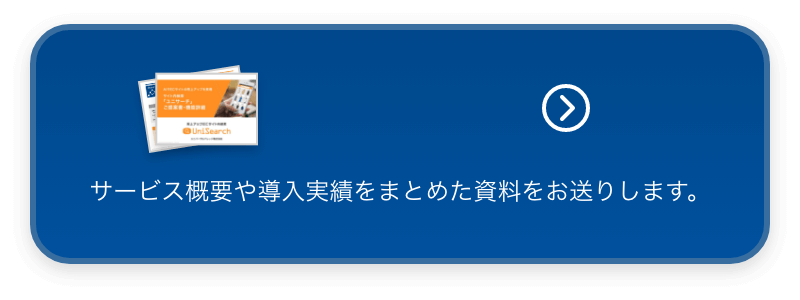BtoB-ECのコンバージョン率をアップする10の施策を解説
「ECサイトを運営しているのに思ったように売上が伸びない」「アクセスはあるのに購入に至らない」と悩むEC担当者は少なくありません。BtoB-ECでは、BtoC(企業対消費者間取引)と比べて商品点数が多く、ユーザーが目的の商品にたどり着くまでに時間がかかる傾向があります。そのため、購入までの導線が複雑になりやすく、CVR(コンバージョン率)の改善は重大な課題の1つです。
当記事では、BtoB-ECの平均的なCVRと低下の原因、CVR改善策を解説します。現状のECサイトを分析し、自社の課題を特定した上で、サイト改善施策を取り入れましょう。
1.BtoB-ECとは
BtoB-ECとは、「Business to Business Electronic Commerce」の略称で、企業同士がインターネット上のECサイトを通じて商品やサービスの受発注を行う仕組みを指します。従来はFAXや電話などのアナログな手段が主流でしたが、近年はWeb受発注システムを導入して業務効率化や販路拡大を進める企業が増えています。
BtoCと異なり、BtoBでは法人間取引特有の掛け売りや定期購入といった商習慣があり、EC化によってデジタル上でスムーズに管理できるのが特徴です。インターネット環境とパソコン・スマートフォンさえあれば、時間や場所を問わず受発注が可能となり、企業活動の効率化と取引スピード・成約率の向上を図れます。
2.BtoB-ECの平均的なコンバージョン率(CVR)
コンバージョン率(CVR)とは、ECサイトを訪問したユーザーのうち、実際に商品購入へ至った割合を示す指標です。一般的なBtoC-ECでは、業界平均が3%前後とされており、消費者向け家電ECでは約1.7%と低めに出ることもあります。中でも、高額商品は比較検討に時間を要するため、EC業界では購入率が下がる傾向です。
一方、BtoB-ECでは繰り返し購入や目的買いが中心となるため、比較的CVRは高く、20%を超える企業も多く見られます。
実際にユニサーチ導入企業のCVRランキング調査では、工具・資材業界で40%以上、食品・ギフト系分野でも20%を超えるBtoBサイトが上位にランクインしています。つまり、BtoB-ECはBtoCよりも購入率が高く出やすい傾向があり、効果的な施策を導入することでさらに改善の余地があると言えます。
2-1.ECサイトのCVRを計算する方法
ECサイトのCVRは「購入に至った割合」を数値化するもので、基本的な計算式は「CVR=購入数(CV)÷サイト訪問者数×100」です。本来であれば正確な「人数」で算出するのが理想ですが、実際には同一利用者が複数回訪問するケースも多いため、一般的には「ブラウザ単位」で計測する方法が推奨されます。
たとえば、ECサイトに2,000のブラウザからの訪問があり、そのうち20件の購入が発生した場合、20÷2,000×100=1%という計算になります。ブラウザ数や訪問者数を正確に把握できない場合は、指定期間内のセッション数を基準にする方法もあります。いずれの場合も、自社サイトのデータを同じ基準で継続的に計測し、推移を確認することが重要です。
3.BtoB-ECのCVRを上がりにくくする主な原因
BtoB-ECのCVRが思うように上がらない背景には、導線設計や情報不足など、複数の要因が考えられます。ここからは、BtoB-ECのCVRが上がりにくい主な原因を整理して解説します。
3-1.そもそも商品にたどり着けない
導線設計が不十分で「ユーザーがほしい商品にすぐにたどり着けない」状態であるために、機会損失を生んでいる場合もあります。たとえば、「カテゴリで検索できず指定の商品が簡単に見つからない」「過去に購入した商品をもう一度探し出すのに手間がかかる」といった不便さは、ユーザーにとって多大なストレスです。
また、サイト内検索の精度が低い場合や、検索結果の表示速度が遅い場合も障壁になります。探している商品がすぐに表示されなかったり、意図しない結果が返ってきたりすると、ユーザーは離脱し、他社サイトへ移動する可能性が高まります。その結果、顧客ロイヤルティの低下や売上の減少につながり、長期的にはサイト全体の信頼性を損ねかねません。CVRを効果的に高めるには、ユーザーがスムーズに商品を探せるようサイト内検索機能を最適化し、利便性を向上させる必要があります。
3-2.ユーザーのペルソナ設計を誤っている
ペルソナとは、年齢や職業、価値観や購買動機といった情報をもとに自社が狙うターゲットユーザー像を具体的に描いたものです。しかし、ペルソナが曖昧で実際の顧客層とずれていると、ECサイトに訪問したユーザーが「自社向けではない」と感じ、購入行動に至りにくくなります。
反対に、「誰にでも当てはまるようなECサイト」を目指すと、結果的に誰にも響かない構成となり、ユーザー満足度も下がります。ペルソナを設計する際は、実際の顧客データを参考にしながら属性・行動・価値観を整理し、具体的な人物像として描くことがポイントです。
3-3.ページの読み込み速度が重く使いづらい
BtoB-ECにおいてページの読み込み速度が遅いと、目的の商品にたどり着く前にストレスを感じ、離脱や直帰につながるケースが増えます。特に商品画像や外部タグが多いページでは表示が重くなりやすく、検索エンジンの評価低下による検索順位の下落で流入が減少するリスクも伴います。
また、待ち時間の長さは顧客満足度を下げ、リピーターの減少にも影響します。こうした影響を避けるには、画像やファイル容量の軽量化、不要なスクリプトや外部タグの整理、ファーストビューの優先表示などの工夫が有効です。ページの読み込み速度は「快適に買い物ができるかどうか」を左右する要素であり、改善に取り組むことでCVR向上の土台を築けます。
3-4.購入に至るまでのコンテンツが足りない
ECサイトでユーザーが購入に至るまでには商品情報だけでなく、比較や利用シーンをイメージできるような補助的なコンテンツが必要です。特に、スモール型BtoBサイトの場合、ユーザーニーズに合う記事やコラムといったコンテンツが不足していると、外部からの新規流入を得られず、機会損失につながりかねません。
ただ商品を並べるだけでは「なぜこの商品を選ぶべきか」が伝わらず、ユーザーが検討段階で離脱してしまう恐れがあります。ユーザーにとって価値を感じる情報を継続的に提供することは、ブランド認知や購買意欲の向上に効果的です。ECサイトでコンテンツを展開する際は、自社の商品やサービスと相性のよいテーマを選び、ユーザー目線で有益な情報を発信しましょう。
3-5.商品画像や商品情報が足りない
BtoB-ECにおいて、商品ページに十分な情報が揃っていないことはCVRを下げる要因となります。カタログ番号やスペックだけが記載されて画像が乏しいECサイトでは、ユーザーが実際に使用するイメージを持ちにくく「本当にこの商品でよいのか」と不安が残ります。レビューが極端に少ない場合も、購入後の使用感が分からず、意思決定を後押しできません。
一方で、ランキング表示や活用事例といったコンテンツがあれば「多くの人に選ばれている」という安心感や、利用シーンを具体的に想像できる情報が提供され、購買意欲を高められます。ユーザーが商品を購入する際は、「失敗したくない」という心理が強く働きます。使用シーンが思い浮かぶような詳細な情報や豊富な商品画像、他者の評価が揃うことで意思決定のハードルが下がり、購入に至りやすくなるでしょう。
4.BtoB-ECのCVRを改善する10の施策
BtoB-ECのCVRを高めるには、ユーザーが安心して購入できる環境づくりが不可欠です。ここでは、BtoB-ECのCVR改善に役立つ施策を紹介します。
4-1.サイト内検索を最適化する
商品数が膨大なECサイトで、ユーザーが目的の商品をすばやく見つけられるようにするには、サイト内検索の最適化は必須です。たとえば、規格やスペックで絞り込めるファセット検索があれば、数十万点規模の商品を扱うECサイトでもスムーズに商品を探せます。
また、BtoBでは型番や品番で検索するケースが多いため、入力途中で候補を提示する「型番サジェスト機能」があると利便性が向上します。こうした仕組みを持つサイト内検索ツールを導入することで探しやすさが向上すれば、購入までの導線が短縮され、売上アップが可能です。
「ユニサーチ」は、AIによる検索結果の自動最適化や顧客別のパーソナライズ表示にも対応しているサイト内検索ツールです。規格・属性条件検索や型番サジェスト、法人別の価格制御なども備えています。
4-2.リピート購入をしやすい設計にする
BtoB取引では新規顧客の獲得に加え、既存顧客からのリピート注文を増やすことが収益の安定化には必要です。ECサイトにおいても同様に、ユーザーが繰り返し購入しやすい設計にすると、CVR向上を図れます。たとえば、サイト内検索ツールの機能である「履歴サジェスト」を利用すれば、過去に検索したキーワードを自動で表示し、入力の手間を省くことで、再購入のスピードを高められます。購入履歴や閲覧履歴をトップページやマイページに表示し、過去購入した商品にアクセス・再注文しやすい設計にすることも効果的です。
また、商品の検索結果画面において、顧客ごとに頻繁に購入される商品を上位に表示することでも再注文を促進できます。サイト内検索ツール「ユニサーチ」には、履歴サジェストや顧客ごとの自動最適化機能など、リピート購入を後押しする機能が搭載されています。
4-3.サイトトップのナビゲーションを見直す
ECサイトのトップページは、ユーザーが最初に訪れる入口です。そのため、ナビゲーション設計を見直し、ユーザーが目的の商品や情報にたどり着きやすくすることは、結果的にCVR改善につながる重要な施策です。
たとえば、グローバルナビゲーションやパンくずリストが煩雑になっている場合は一度整理し、現在位置や関連ページへの移動を分かりやすくしましょう。また、随所に内部リンクやハイパーテキストを設けると、商品ページや関連記事への誘導が強化され、回遊性が向上します。ナビゲーションを構造化することはユーザビリティの向上だけでなく、SEO対策にも有効です。
4-4.まとめ買いしやすい設計にする
大量注文・目的買いが多いBtoB-ECでは、複数の商品をまとめて、短時間で効率的に注文できる仕組みも重要です。一般的なECサイトでは商品を購入する場合、「商品を検索する→購入する商品の詳細ページを開く→数量を選択する→カートへ入れる→次の商品を検索する」の繰り返しになります。購入する商品を1点ずつカートに入れると作業効率が悪いため、あらかじめ商品一覧画面に数量変更メニューとカートへ投入するボタンを設置することで、不要な動作を減らし、日々の発注操作をストレスなく運用してもらうことが可能になります。
また、商品番号と数量を入力するだけで商品を簡単に注文できるシステム「クイックオーダー(一括注文)」機能も、複数の商品を注文する場合などに重宝される機能の1つです。
4-5.商品ページのレイアウトを改善する
「いい商品なら売れる」という考えはECサイトでは通用しません。CVRを改善するには、商品ページのファーストビューで商品名・画像・価格などの必須情報を瞬時に提示し、取引先が商品を正確に理解して購入を決断できるように、商品ページを最適化することが必要です。
その際、商品の詳細情報(サイズ、仕様、価格、納期など)を分かりやすく記載すると、ユーザーの商品理解をより深められます。また、CTAボタンは視認性の高い色やサイズで強調し、分かりやすい文言を使いましょう。レビューや比較情報を併せて掲載すれば、ユーザーは商品の信頼性や他商品との違いを確認しやすくなり、購入判断をサポートできます。
4-6.ターゲットキーワードから商品にかかわるコンテンツを作る
BtoB-ECの集客を強化するには、ターゲットキーワードを起点にしたコンテンツ作成も効果的です。ターゲットキーワードとは、見込み顧客が検索する語句を考えた上で選定するキーワードのことです。「業務用調味料」「オフィス家具 価格比較」など、商品やサービスに直結する言葉を選びましょう。
ターゲットキーワードをもとに「導入事例」「選び方のポイント」「業界の最新動向」など、ユーザーの意思決定を支える有益な記事を展開すれば、SEO効果が高まり、ウェブ検索エンジンからの流入増加が期待できます。単なる商品説明にとどまらず、購買の背景や利用シーンをイメージさせるコンテンツを用意することは、見込み客にとって「役立つ情報源」となり、購買意欲を高められます。
4-7.レビュー機能を搭載する
BtoB購買は合理性が優先されるためレビュー機能が必須ではないものの、状況次第で大きな効果を発揮する場合があります。たとえば、初めて取引する顧客の場合、同業他社や他ユーザーの声は安心材料になり、不安解消につながります。また、高額商品・専門商材においては購入の意思決定に時間がかかるため、第三者の実体験に基づくレビューが比較検討時の強力な判断材料となる可能性もあります。
しかし、法人取引では発注者が限られることから、レビュー自体を集めるハードルが高く、数が少ない傾向にあります。十分なレビューが集まらず、形だけのレビュー欄は購買率が低下する恐れがあるため、リスクを踏まえて検討が必要です。
4-8.顧客が使いやすい決済手段に対応する
BtoB-ECではBtoCと比べて決済方法や支払いタイミングが多様であり、取引形態に応じた柔軟な対応が求められます。前入金や受取時支払いのほか、ニーズが高いのが「掛け売り・掛け払い」です。請求書払いを導入することで取引先は資金繰りがしやすく、支払い処理の効率化も図れます。一方で、未払いリスクや入金管理の負担が発生するため、適切な与信管理や請求フローの整備が必要です。
また、コーポレートカードによるクレジット決済や口座振替など、企業によって好まれる支払い手段は異なるため、できる限り多様な決済方法を用意しましょう。決済手段を拡充することで、新規顧客の取り込みや取引機会の損失防止ができれば、結果としてCVRの改善にも直結します。
4-9.チャットボットやFAQツールを導入する
BtoB-ECでは、購入前の疑問や不安が解消されないことが原因で、購入に至らず離脱されることも少なくありません。こうした課題を解決する有効な手段が、チャットボットやFAQツールの導入です。チャットボットは、ルールベース型やAI型によってユーザーの質問に即座に応答でき、営業時間外でもサポート可能です。問い合わせや商品提案、ホワイトペーパーへの誘導など多彩に活用でき、商談機会の拡大にも寄与します。
一方で、FAQツールは送料・納期・返品条件といった定型的な質問を体系化し、ユーザーが自ら問題を解決できる仕組みを提供するものです。これにより、問い合わせ対応の効率化、オペレーターの負担軽減、回答品質の均一化を図れます。簡易な質問はFAQツールでカバーし、複雑な内容はチャットボットに任せるといった運用方法を実施すれば、CX(顧客体験)向上とCVR改善の両方を実現できるでしょう。
4-10.オンラインとオフラインの動きを連携させる
BtoB-ECにおいては、ECサイトと対面営業を分断せずに連携させる「オムニチャネル化」も必要です。オムニチャネルとは、ECサイト・実店舗・電話・メール・SNSなど複数のチャネルをシームレスにつなぎ、顧客がどの接点からでも商品を検索・購入ができる仕組みのことです。
たとえば、代理注文機能があれば、電話やFAXで受けた注文を自社の担当者が代理でECサイトに入力することで、個別に処理せずとも、受注処理を行うこともできます。BtoB-ECサイトを構築してもすべての受発注をECサイトに完全に移行するのは難しく、従来の電話やFAX注文を希望する顧客への対応も必要となります。
代理注文のような機能があれば、営業が得意先に伺って商談の場で代理で注文を受けることもでき、顧客にとって利便性の高い購買体験を提供できます。今後のBtoB-ECを成長させるには、顧客がスムーズに購買を進められる導線を整えることが欠かせないでしょう。
まとめ
BtoB-ECでは、商品情報の不足やナビゲーションの不備、検索機能の弱さなどがCVR低下の原因となります。CVRを改善するためには、まずサイト内検索によってユーザーが目的の商品にすばやくたどり着ける環境を整えることが大切です。さらに、リピート購入しやすいサイト設計、コンテンツマーケティングの導入、チャットボットやFAQツールの導入なども効果的な施策です。
今すぐCVR改善に取り組みたい場合におすすめの解決策は、サイト内検索の最適化です。サイト内検索ツールを導入することで、ユーザーの利便性を向上しながらCVR改善を図れるさまざまな機能をECサイトに付与できます。BtoB向けのサイト内検索ツールをお探しの方は、AIによるパーソナライズ機能や型番・履歴サジェスト機能などを搭載した「ユニサーチ」をぜひご利用ください。
関連する記事
新着記事
人気記事
一覧ページへ戻る
-
「ユニサーチ」製品情報
ECサイトの売上アップを らくらく実現する商品検索エンジン

Q&A よくあるご質問
サイト内検索「ユニサーチ」について、お客様から寄せられたよくあるご質問とその回答をご紹介しています。