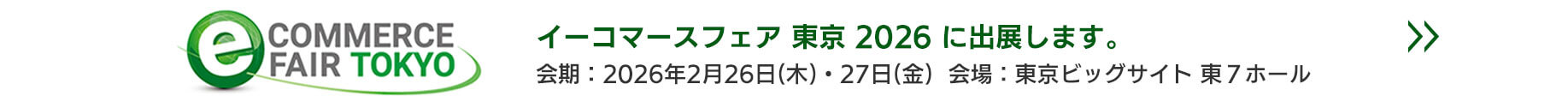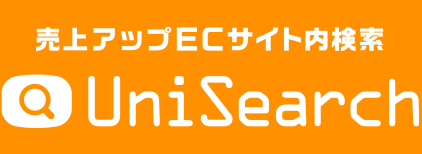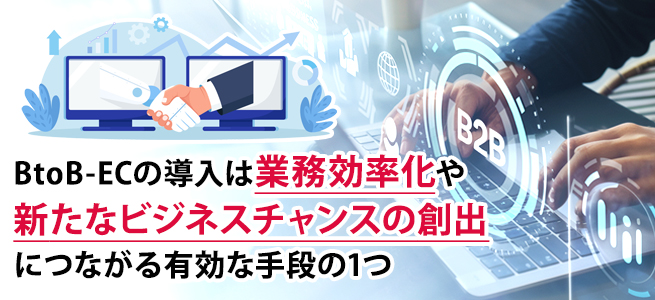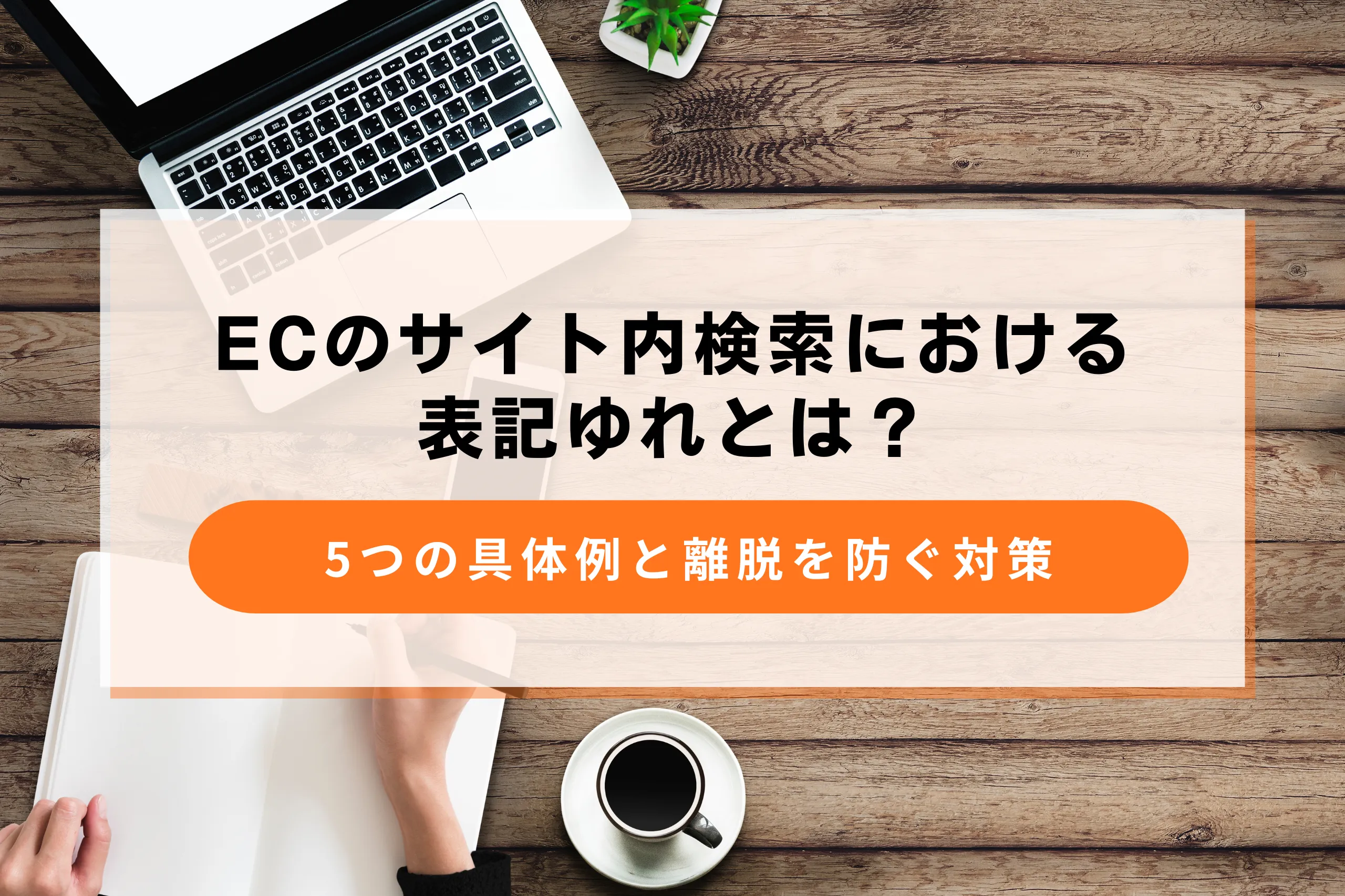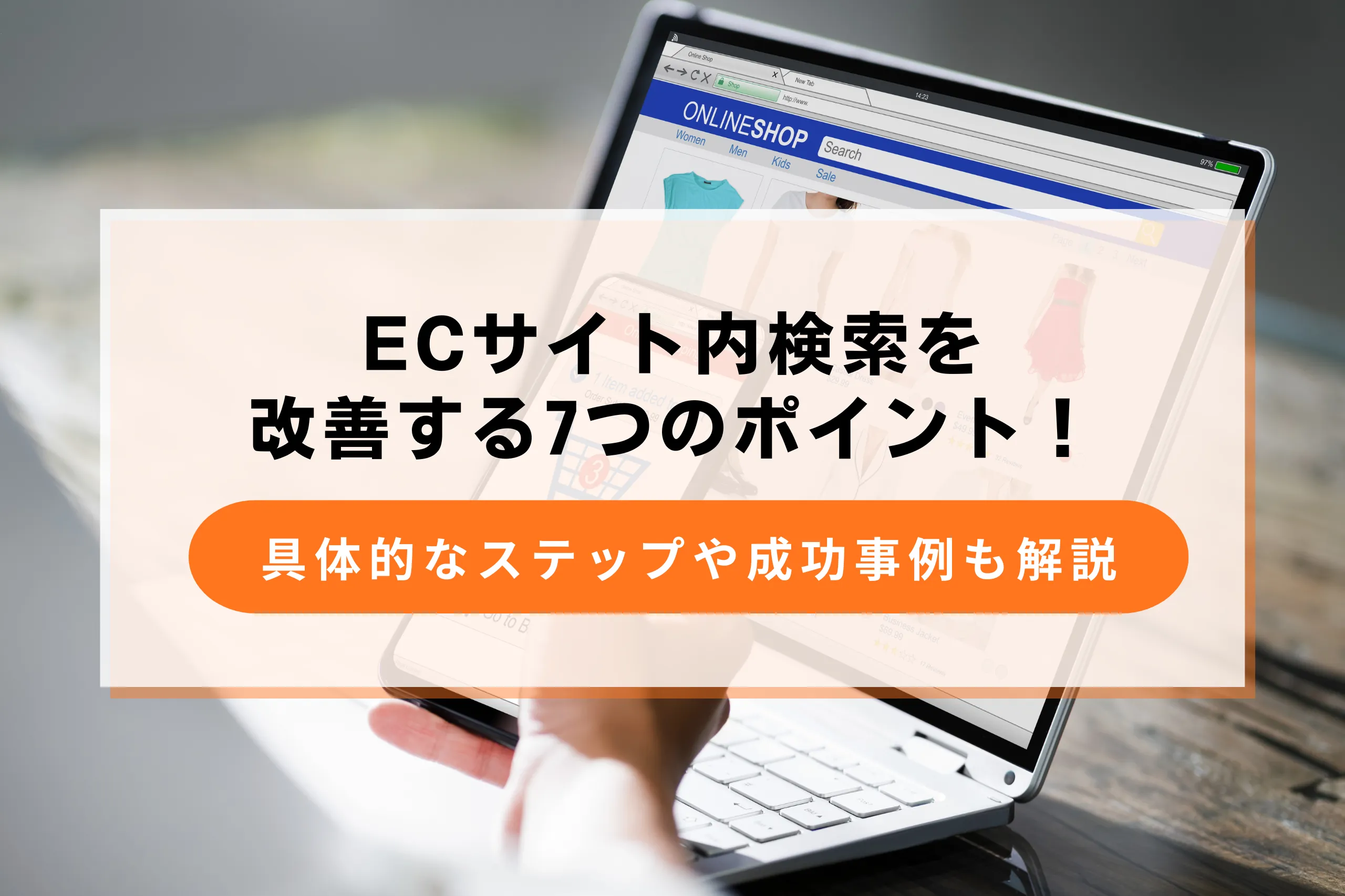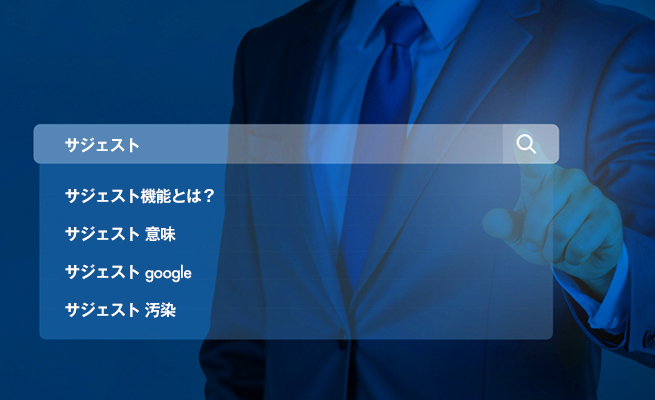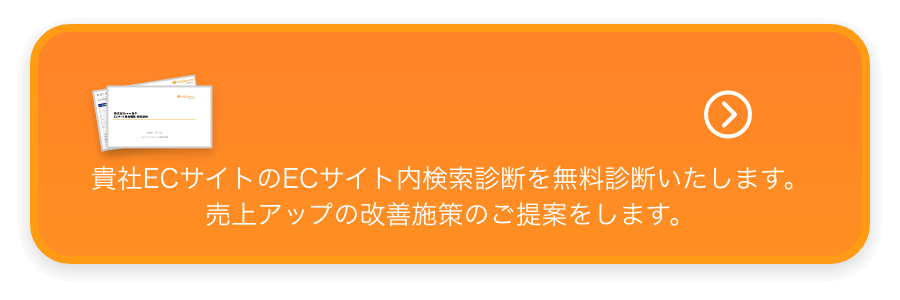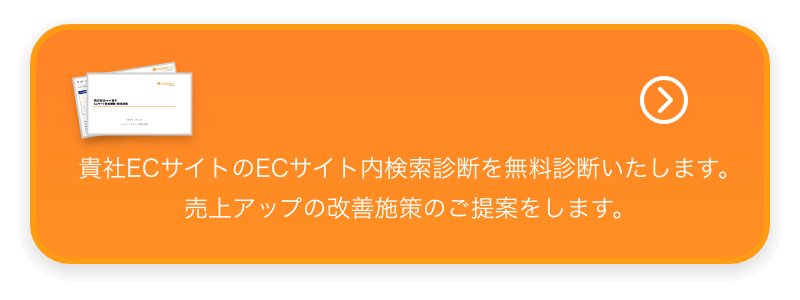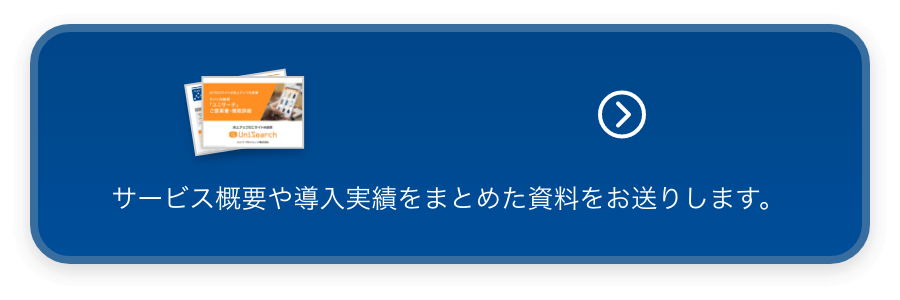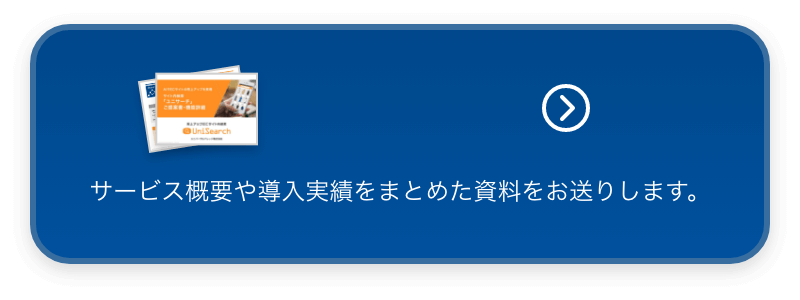BtoB-ECとは?現在の市場規模や構築方法・よくある課題を解説
従来EDIに使用していたISDN回線が廃止されたこともあり、企業間取引においてBtoB-ECの導入が急速に進んでいます。BtoB-ECを導入すれば、従来の電話やFAXを使った業務と比べて、受発注業務の効率を大きく改善できるため、市場規模は年々拡大中です。
一方、導入を検討するにあたって、「どのような仕組みを導入すればよいのか」「構築時に何に注意すべきか」といった課題が生じることも少なくありません。
この記事では、BtoB-ECの基礎知識から、市場動向、導入メリット、構築方法、よくある課題と対策方法まで解説します。
1. BtoB-ECとは
BtoB-ECとは「Business to Business Electronic Commerce」を略した言葉で、企業間取引をインターネット上で行う仕組みを指します。従来の電話・FAX・メールを用いた受発注や請求処理などを、電子的に効率化することが目的です。
企業がBtoB-ECを導入すれば、場所や時間を問わず業務が可能になり、業務負担の軽減や人的ミスの削減が期待できます。
1-1. BtoB-ECとBtoC-ECの違い
BtoB-ECと混同されやすいのがBtoC-ECです。BtoC-ECは企業が消費者に商品やサービスを提供する電子商取引であり、主に個人を対象とします。購入に至るまでの判断が短く、対象によってサービスや価格が大きく変動することはありません。
一方、BtoB-ECは企業同士の取引であり、高額な商材や継続的な取引が多く見られます。購入決定には複数人の承認が必要になる場合が多く、意思決定には時間がかかる傾向があります。取引先によって価格や取扱商品を変更できる機能や、掛け売り・請求書払いなどの多様な決済手段も必要です。クローズドサイトとしての運用が多い点も違いです。
1-2. BtoB-ECとEDIの違い
EDI(Electronic Data Interchange)とは、企業間で発生する発注書や請求書などのやり取りを電子化し、インターネットやISDN回線で電子データを交換する仕組みです。紙媒体に比べ、入力ミスや送付ミスを防げる上、処理スピードも向上します。大手企業を中心に広く導入されていますが、互換性のある業務システムが必要で、導入コストも課題です。
また、2024年にはINSネット(ISDN回線)のサービスが終了しました。従来のISDN回線を使うEDIを利用していた企業は、インターネット回線で使えるWeb-EDIやBtoB-ECへの移行を検討する必要があります。
BtoB-ECは、Webブラウザを通じて操作でき、取引先が専用のシステムを用意する必要がありません。売上拡大や新規顧客の獲得も視野に入れた設計が可能で、柔軟な対応が求められる小口取引にも向いています。
2. BtoB-ECの市場規模
BtoB-EC市場は年々拡大しています。経済産業省の調査によると、2023年の国内BtoB-EC市場規模は465兆2,372億円でした。前年から10.7%増加しており、右肩上がりの成長を見せています。EC化率も40.0%に達しており、商取引全体の約4割がEC化されている状況です。
2-1. BtoB-EC化率が拡大している業種
BtoB-EC市場規模の業種別データをみると、特に製造業のEC化が著しく進んでいることが伺えます。
| 大分類 | 中分類 | 2021年 EC市場規模(億円) | 2021年 EC化率 | 2022年 EC市場規模(億円) | 2022年 EC化率 | 2023年 EC市場規模(億円) | 2023年 対前年比 | 2023年 EC化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設 | 建設・不動産業 | 208,558 | 14.3% | 234,598 | 15.2% | 271,277 | 15.6% | 16.9% |
| 製造 | 食品 | 271,027 | 67.2% | 296,443 | 70.7% | 355,307 | 19.9% | 75.0% |
| 繊維・日用品・化学 | 376,509 | 47.9% | 447,337 | 49.9% | 451,456 | 0.9% | 52.4% | |
| 鉄・非鉄金属 | 252,529 | 42.7% | 286,620 | 44.1% | 309,151 | 7.9% | 46.2% | |
| 産業関連機器・精密機器 | 181,284 | 40.7% | 207,734 | 42.0% | 221,639 | 6.7% | 44.6% | |
| 電気・情報関連機器 | 391,121 | 64.2% | 450,282 | 66.3% | 451,318 | 0.2% | 69.6% | |
| 輸送用機械 | 542,170 | 74.3% | 588,775 | 76.7% | 735,495 | 24.9% | 80.6% | |
| 情報通信 | 情報通信 | 166,975 | 21.8% | 182,616 | 22.3% | 223,984 | 22.7% | 23.4% |
| 運輸 | 運輸 | 110,884 | 19.2% | 133,433 | 20.9% | 139,465 | 4.5% | 22.5% |
| 卸売 | 卸売 | 1,006,059 | 32.3% | 1,128,794 | 34.9% | 1,212,499 | 7.4% | 37.5% |
| 金融 | 金融 | 141,237 | 23.2% | 160,314 | 23.8% | 184,548 | 15.1% | 25.2% |
| サービス | 広告・物品賃貸 | 43,568 | 15.5% | 44,596 | 15.9% | 47,957 | 7.5% | 16.8% |
| その他 | 小売 | 29,875 | – | 34,041 | – | 40,579 | 19.2% | – |
| その他サービス業 | 5,277 | – | 6,771 | – | 7,697 | 13.7% | – |
出典:経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書」
特に注目されるのが、「輸送用機械」「食品」「電気・情報関連機器」などの業種です。いずれも高い水準を記録している背景には、製品が標準化されており、オンラインで取引しやすいという事情があります。また、2023年は外食や宿泊需要が回復し、業務用食品の取引が活性化したことも、食品分野のEC化を後押ししました。
卸売業も拡大傾向にあり、大手流通業を中心にデジタル化の流れが加速していると考えられます。
分野によって成長のスピードに差はありますが、全体としてはEC化が着実に進展している状況です。
2-2. BtoB-EC化率が拡大している背景
BtoB-EC化が進む背景には、複数の社会的・技術的な要因があります。
- DX推進の加速
長時間労働の是正やテレワークの推進により、非効率な業務の見直しが進み、電話やFAXを使ったアナログ業務のデジタル化が進行しました。ECサイトであれば業務を自動化でき、デジタル化に合わせて業務フローを変革できます。 - BCP(事業継続計画)対策の重要性
自然災害や感染症拡大により、対面での営業活動をストップせざるを得ない状況下において、クラウド管理によるデータ保全や遠隔操作が可能なBtoB-ECの有用性が再評価されています。 - 取引先の影響
顧客や競合のEC化が進む中、取引の円滑化を図るために自社でも導入を進める企業が増えています。 - 商習慣への柔軟な対応
取引先ごとの価格設定や閲覧制限など、日本独特の取引形態に対応するBtoB-ECシステムが開発されたことで、導入のハードルが下がりました。
こうした要因が複合的に作用し、BtoB-EC化率の上昇を後押ししています。
3. BtoB-ECの種類
BtoB-ECには大きく分けて「クローズド型BtoB」と「スモール型BtoB」、「マーケットプレイス型BtoB」の3種類があります。どちらも企業間の受発注業務を効率化する手段ですが、目的や運用形態には明確な違いがあるため、自社の取引先や業務スタイルに応じて選択することが重要です。自社に最適なBtoB-ECを選ぶためにも、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
3-1. クローズド型BtoB
クローズド型BtoBは、特定の取引先に限定して利用される非公開のECサイトです。サイトを利用するにはログインが必要で、検索エンジンからも見つからないよう設計されています。主に、既存顧客との継続的な取引を効率化するために利用されるサイトです。
クローズド型BtoBでは、取引先ごとに価格や取扱商品情報を変更できる柔軟性があり、企業間の商習慣にあわせて、個別に条件を設定できる点が大きなメリットです。定期的に一定量を取引する企業同士にとっては、業務の効率化が期待できます。
ただし、新規顧客の流入は見込めないほか、利用者数が少ない分使い勝手が悪いシステム設計になりやすく、操作が複雑で導入効果が出にくいサイトも見られます。効果的な運用には、ユーザー目線での設計が欠かせません。
3-2. スモール型BtoB
スモール型BtoBは、一般的なBtoCのECサイトに近い形で運営する公開型のECサイトです。検索エンジンからの流入も可能で、日本全国あるいは海外の企業もターゲットにできます。
中小企業や新規顧客を取りこぼさず、販路拡大や売上増につなげられる点がメリットです。小規模な取引や遠方の企業とも接点が持てるため、営業リソースが限られる企業にとって、スモール型BtoBは販路拡大に有効な手段と言えます。
また、ECサイト構築のハードルが比較的低く、短期間で立ち上げられる点も魅力です。ただし、将来的なアクセス増に備えた設計が求められる場合もあります。
3-3. マーケットプレイス型BtoB
マーケットプレイス型BtoBは、複数の企業が参加し、商品やサービスを販売するプラットフォームです。マーケットプレイス運営者の顧客基盤をもとに集客を行えるため、新規取引先の開拓や市場拡大を目指す企業に適しています。
マーケットプレイス型BtoB ECサイトの主な例は以下の通りです。
- Amazonビジネス
- スーパーデリバリー
- NETSEA
プラットフォーム側がECサイトとして必要な各種機能を提供しているため、サイト構築や管理の手間がなく、すぐに販売に参入できる点が大きなメリットです。
ただし、プラットフォームに複数の売り手と買い手が参入するため、ライバルとの競争が激しくなる点に注意が必要です。加えて、デザイン上や機能上の制約が多く、自社独自のブランディングなどは難しくなります。
4. BtoB-ECを企業が取り入れるメリット
人手不足や働き方改革が進む中、BtoB-ECの導入は多くの企業にとって、業務効率化や新たなビジネスチャンスの創出につながる有効な手段の1つです。以下では、BtoB-EC導入企業が得られるメリットを3つ解説します。
4-1. 業務負担が削減できる
従来の取引方法では、電話やFAXによる注文確認、手書きの発注書の処理、在庫や納期の問い合わせ対応など、多くの手作業が発生していました。BtoB-ECなら、これらの作業をある程度自動化可能です。
BtoB-ECを導入すれば、都度電話などで注文を受けて見積もりを作ったり納期を確認したりする作業がなくなり、商品の確認から発注まで顧客側で完結できます。受発注データはリアルタイムで反映されるため、在庫や納期の確認もスムーズです。商品スペックや単価もWeb上で確認でき、問い合わせ対応の負担も軽減されます。
業務フローを大幅に簡略化できれば、人的リソースの節約も可能です。
4-2. ヒューマンエラーを削減できる
アナログな業務には、人間の作業によるミスがつきものです。聞き間違いや手入力ミス、帳票の紛失などを完全になくすことはできません。これら受注業務のミスは、誤発注や納期遅延といったトラブルの原因になりやすく、信用問題に発展することもあります。
ECサイトを活用すれば、注文データは顧客が直接入力するため、ヒューマンエラーの発生リスクが大きく下がります。注文履歴や在庫状況もシステム上に一元管理され、確認作業や修正対応の手間も省けます。
また、帳票作成やファイルの管理もデジタルで完結するため、紙の保管コストや押印作業なども不要です。これにより、正確性の高い取引を実現しつつ、コスト削減が可能です。
4-3. 顧客との接点を増やせる
ECサイトを活用すれば、顧客は24時間365日いつでもアクセスできるようになります。営業時間外でも注文や情報確認が可能となり、受注のチャンスを逃す心配がありません。
特にスモールBtoB型の場合は、検索経由でサイトを訪れた企業との新たな接点が生まれやすくなります。問い合わせや資料請求、カタログのダウンロードをきっかけに見込み客との関係が構築され、営業の起点として活用できるでしょう。
また、ECサイト内にオウンドメディアを設置すれば、検索エンジンからの流入も見込めます。製品に関する記事や導入事例、業界ニュースなどを掲載し、見込み客の関心を高めれば、問い合わせや購入につなげる仕組みの構築も可能です。
このように、BtoB-ECは単なる業務効率化のツールにとどまらず、マーケティングや営業の一環としても機能します。
5. BtoB-ECサイトの構築方法
BtoB-ECサイトを構築する方法には、大きく分けて3つの選択肢があります。
| ASP型 | ASP型はクラウドサービスとして提供されるため、短期間かつ低コストで構築できるのが特徴です。サーバー管理や保守の負担が少ないため、小規模事業者やスタートアップに適しています。ただし、機能のカスタマイズ性は低く、取引先ごとの価格設定や複雑な承認フローなどが必要な場合にはあまり向きません。 |
|---|---|
| パッケージ型 | パッケージ型は、あらかじめ基本機能を備えたソフトウェアをベースに構築する仕組みで、取引先ごとの特別価格や承認フローの追加、基幹システムとの連携なども可能です。中規模以上の企業で、業務効率化と顧客対応の両立を図りたい場合に有効です。 |
| フルスクラッチ開発 | フルスクラッチ開発は、ゼロからシステムを開発するため、業界特有の商習慣や取引条件にも柔軟に対応できます。開発には多くの時間とコストがかかるため、大規模企業や業務要件が複雑な企業に向いた方法です。 |
それぞれの特性を理解した上で、自社の取引形態や業務フローに適した方法を選びましょう。
5-1. BtoB-ECサイトに求められる機能
BtoB-ECサイトには、BtoCとは異なる業務要件に対応する多様な機能が必要です。
- 顧客情報の管理機能
BtoBにおいては、顧客ごとの企業情報や取引条件・履歴などを一元管理する機能も必要です。取引先ごとに価格・表示商品が異なる事があるBtoB ECでは、契約内容に応じて表示を制御する機能のほか、BtoBでは後払いが一般的なため、締め日・支払期日・与信限度額の設定ができる仕組みも求められます。 - 見積り管理機能
購入前に見積書の提出が必要な取引が多いため、自動見積やPDF出力機能の搭載が求められます。 - 請求書の発行機能
適格請求書や合算請求書の自動発行に対応することで、インボイス制度にも対応できます。 - 受発注管理機能
仮注文・在庫引当・出荷指示・納品管理まで、システム上で一元管理できる機能は欠かせません。 - 基幹システムとの連携機能
在庫・販売・会計などの社内システムと連携することで、業務の重複やミスを防ぎます。 - 承認フロー機能
社内での決裁を要する発注には、段階的な承認プロセスを組み込む必要があります。発注ミスや不正を防ぐ意味でも重要です。 - ディスカウント管理機能
取引先別の割引率やキャンペーン価格を設定・反映できる機能も求められます。
企業によっても業務フローが異なるため、すべての機能を備える必要はありません。自社の業務に必要な機能を事前に明確化し、必要な機能を厳選しましょう。
6. BtoB-ECサイトによくある課題と対策
BtoB-ECサイトは業務効率化や売上向上に効果的ですが、導入や運用の過程でさまざまな課題が生じることもあります。システム構築に多額の投資がかかるため、失敗すれば大きな損失にもなりかねません。
以下では、BtoB-ECサイトによくある課題とその対策を解説します。
6-1. 業務フローの独自性が高く構築負担が大きい
BtoBビジネスでは、企業ごとに業務フローや商習慣が異なることが多く、汎用的な仕組みでは対応が難しい傾向にあるのが課題の1つです。結果として、ECサイトの構築やカスタマイズに多くの時間と費用がかかる可能性があります。
重要なのは、早めに業務フローを正確に把握し、現場と開発担当の間で認識を一致させることです。初期段階で関係者と十分に協議し、仕様を変更するリスクを抑えると、構築後のトラブルを防止できます。また、変更頻度の高い業務はECサイトに機能を持たせ、安定している業務は基幹システム側に任せるなど、システムの役割分担も有効です。
6-2. 業務が属人化しておりEC化が進まない
BtoB取引では、特定の営業担当者ごとに、それぞれ長年の経験と個別の判断に基づいて業務を進めるケースが少なくありません。こうした属人化も、ECサイトによる業務の標準化や自動化を妨げる要因の1つです。
有効な対策は、まず既存業務の棚卸しを行い、手順やルールを明文化することです。取引内容や割引条件、承認フローなどを可視化し、誰が見ても業務を再現できる状態を整えなければなりません。
属人化した業務の見直しには、関係者の理解と協力が必須です。EC化が担当の役割を奪うのではなく、むしろ付加価値の高い仕事に集中できるようになる点を強調すれば、前向きな意識を引き出せるでしょう。
6-3. CXが悪く顧客が利用してくれない
ECサイトを構築しても、使い勝手が悪ければ顧客は利用してくれません。特に検索機能や表示速度、入力のしやすさなどは、ユーザー体験(CX)に直結します。たとえば、型番検索しかできない・在庫が見えない・操作が複雑などの問題があると、積極的な利用は望めないでしょう。
ECサイトには、顧客目線での設計が欠かせません。検索やサジェスト機能の導入、豊富な決済方法への対応、パーソナライズ表示などはCXの改善に大きく貢献する要素です。開発段階で得意先の意見を取り入れ、実際の使用感を重視した設計を行えば、ECシステム導入後の定着率が高まります。
まとめ
BtoB-ECを導入すると、業務負担や人的ミスの軽減、新規顧客獲得などのメリットが得られます。一方で、業務フローが複雑で構築が難しかったり、属人的な業務がEC化の障害となったり、使いにくいシステムで顧客離れが起きたりといった課題もあります。そのため、導入前に自社の業務を明確に整理し、取引先の目線で使いやすいサイトを作ることが不可欠です。
CXを改善するには、サイト内検索の最適化が重要になります。ユニサーチは顧客の購買行動データをAIが学習し、使いやすく、売れやすい検索結果を生成するECサイト向け検索ツールです。使い勝手の良いECサイトを構築したい方は、ぜひユニサーチの導入をご検討ください。
関連する記事
新着記事
人気記事
一覧ページへ戻る
-
「ユニサーチ」製品情報
ECサイトの売上アップを らくらく実現する商品検索エンジン

Q&A よくあるご質問
サイト内検索「ユニサーチ」について、お客様から寄せられたよくあるご質問とその回答をご紹介しています。